電気工事士の人材紹介が禁止?法律違反?安全な採用方法を解説
- 現場作業を行う電気工事士の人材紹介は、職業安定法により原則禁止されている
- 施工管理技士は管理業務中心のため人材紹介が可能な場合があるが、電気工事士は直接作業に従事するため法的扱いが異なる
- 法律を守った採用方法としては、自社サイトやSNSでの応募や、求人サイトを通した応募などが有効的
- 特に電気工事士のような専門性が高い職種は、業界専門の求人サイトを活用することで、資格保有者・経験者に効率よくアプローチできる
- 専門求人サイトは業界に精通したサポート体制があるため、急募案件への対応や採用コストの削減にもつながるメリットがある
「求める資格と経験を持つ人材を、いかに確保するか…」日々、頭を悩ませていらっしゃる採用担当者も多いのではないでしょうか。
その採用手法として「人材紹介」を検討される際には、ぜひ一度立ち止まってください。実は、現場で作業を行う電気工事士の有料職業紹介(人材紹介)は、原則として法律で認められていないことをご存じでしょうか。
この記事では、その法的根拠と見過ごせないリスク、そして法律を遵守しながら本当に求める人材を確実に見つけるための具体的な採用戦略を、分かりやすく解説いたします。
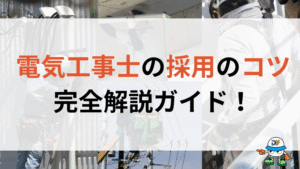
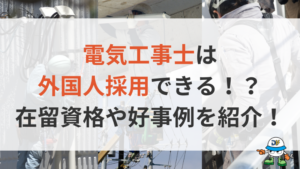
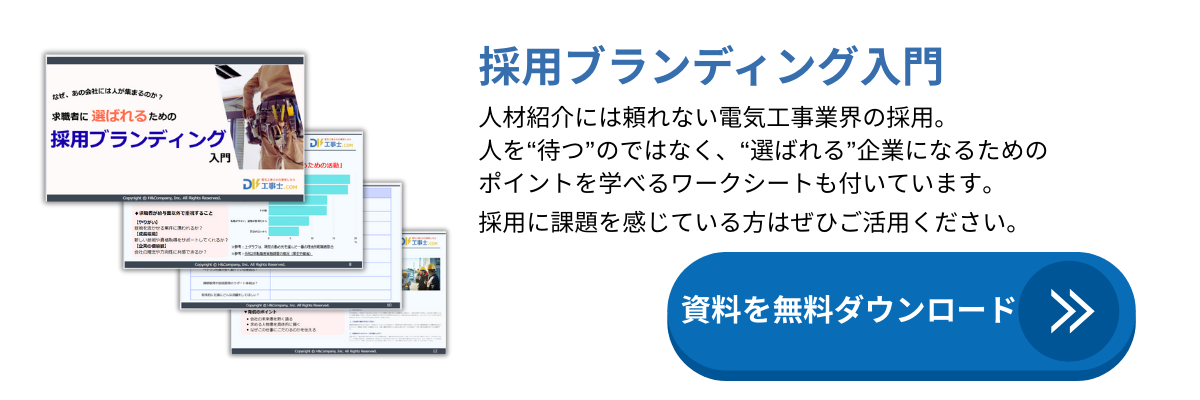
【要注意】法律違反かもしれません! 電気工事士の人材紹介
現場で作業を行う電気工事士の有料職業紹介(人材紹介)は、原則として禁止されています。
その理由の一つに、職業安定法第三十二条の十一第一項があります。
この法律では、建設業において直接的な現場作業に従事する技能労働者(いわゆる職人)については、有料職業紹介事業者による職業のあっせんが禁止されています。
職業安定法 第三十二条の十一第一項によれば、建設業において直接的な現場作業に従事する技能労働者(いわゆる職人)については、有料職業紹介事業者による職業のあっせんが禁止されています。
(取扱職業の範囲)
第三十二条の十一 有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。
② 第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。
もし上記に違反してしまった場合、重い罰則を受ける可能性もあります。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
四 第三十二条の十一第一項の規定に違反したとき。
法令を守り、会社の未来を守るためにも、適切に採用活動を進めることが大切です。
\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
掲載料金の試算もできます!!
≫ホワイトペーパー【「求職者に選ばれるための」採用ブランディング入門】無料ダウンロードはこちら
法律を守った電気工事士の採用方法
前の章では、人材紹介を使う際の法的なリスクについてお伝えしました。
では、電気工事士を安心して採用するには、どんな方法があるのでしょうか?
この章では、法律を守りながら採用するための具体的な方法をご紹介します。
自社の魅力を高め、「直接応募」を増やす
法律を守りつつ、電気工事士を採用するための有効な手段の一つが、自社の魅力を高めて「直接応募(=自社の採用サイトやSNSなどから直接応募を得る)」を増やすことです。この方法では、採用コストを抑えられるだけでなく、企業文化に本当に合う人材と出会える可能性が高まるといったメリットがあります。
まず、自社のホームページや採用ページを見直しましょう。
仕事内容や待遇だけでなく、会社の強み、職場の雰囲気、先輩社員の声、代表者の想いなどを具体的に、そして正直に発信することが大切です。「ここで働いてみたい」と求職者に感じてもらえるような情報提供を心がけてください。
電気工事士専門の「求人サイト」で、質の高い出会いを追求する
人材紹介の法的リスクを避け、資格や経験を持つ電気工事士を確実に見つけるもう一つの有力な手段が、「電気工事士専門の求人サイト」の活用です。
一般的な求人サイトと異なり、こうした専門サイトは、電気工事の仕事を探している、あるいは業界内での転職を考えている意欲の高い求職者が多く利用しています。そのため、自社が求める資格保有経験者へ、より的確にアプローチできる可能性が高まります。これにより、応募段階でのミスマッチを減らし、より質の高い母集団形成が期待できます。
その他、電気工事専門の求人サイトを利用するメリットは、以下の通りです。
1. ターゲット人材にピンポイントでアプローチできる
- 一般的な求人媒体では埋もれがちな電気工事人材に、的確にリーチできます。
- 第二種電気工事士、第一種電気工事士、施工管理技士などの有資格者が集まりやすいのが特徴です。
2. 応募者の“質”が高い
- 業界に特化しているため、職種理解がある人材や経験者が中心です。
- 「電気工事の仕事がしたい」と明確に目的を持っている応募者が多く、採用後のミスマッチが少ないです。
3. 業界に適した訴求ができる
- 原稿テンプレートや実績ある表現が用意されており、職人や電気工事従事者に刺さる表現で訴求が可能です。
- 年収・資格手当・現場の雰囲気など、求職者が気にする情報を伝えやすいです。
4. 急募案件にも対応しやすい
- 「すぐに人がほしい」というニーズにも、スピーディーな掲載で対応可能です。
5. 無駄な費用が抑えられる
- 総合媒体と比べて、無駄な応募対応にかかる工数を削減でき、効率的な採用活動が実現します。
6. 現場ニーズに精通したサポート体制
- 運営スタッフも電気・建設業界に理解があるため、相談しやすいです。
- 採用原稿の作成や、採用戦略の相談もでき、中小企業・個人事業主にも心強い存在です。
求人情報を工夫し、応募者へ迅速かつ丁寧に対応することで、自社にとって本当に価値のある「質の高い出会い」を追求できるでしょう。
≫ホワイトペーパー【「求職者に選ばれるための」採用ブランディング入門】無料ダウンロードはこちら
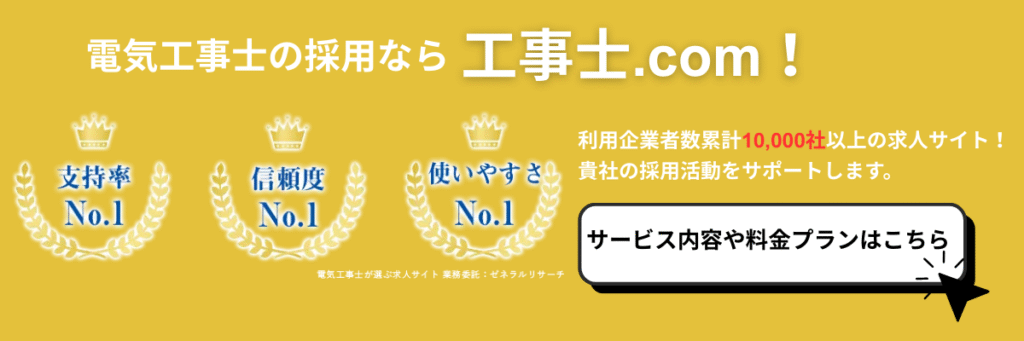
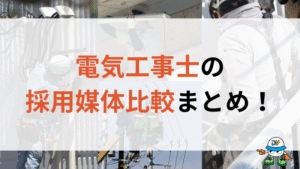
その他の採用方法については、下記記事にてご確認ください。
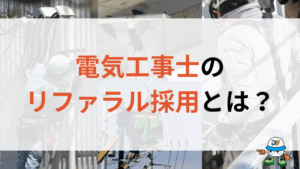
\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
掲載料金の試算もできます!!
Q&A
ここまで電気工事士の採用における法的リスクや、それを回避するための採用方法について解説してきました。
さらに具体的なご質問にお答えします。
以前、施工管理技士は人材紹介で問題なく採用できました。
電気工事士とは、法的な扱いがそんなに違うのですか?
はい、異なると言えるでしょう。
主な理由は業務内容の違いです。
電気工事士は直接的な建設作業に従事するため、記事本文で解説した職業安定法が定める建設業務へ有料職業紹介禁止規定に、実質的に抵触してしまう可能性が極めて高いからです。
一方、施工管理技士は主に現場の管理・監督業務を担い、直接的な建設作業に従事しないため、禁止規定には抵触しない可能性があります。
詳しくはこれらに関連する法律を所管する厚生労働省法令等データベースサービスをご確認ください。
「人材紹介がNG」となると、ハローワーク以外で即戦力となる資格保有経験者を見つけるのは、やはり難しいのでしょうか?
もちろん、ハローワーク以外にも効果的な採用方法はあります。
たとえば、自社のホームページやSNSで会社の魅力を発信し、直接応募を促す手段もありますし、電気工事士に特化した求人サイトを活用するのも有効です。
特化型サイトには、資格や経験を持つ求職者が多く集まっているため、より的確なアプローチが可能です。
その際には、「どんな人に来てほしいか」を明確に伝えることが、即戦力人材を採用するための大切なポイントになります。
職業安定法や関連する法律について、もっと正確な情報を知りたい場合、どこで確認できますか?
職業安定法や労働者派遣法といった法律の条文そのものは、e-Gov法令検索(電子政府の総合窓口)などでご確認いただけます。また、これらの法律を所管する厚生労働省法令等データベースサービスにも、掲載されています。
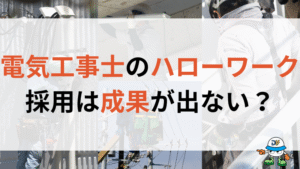
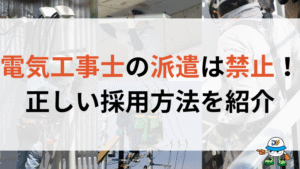
\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
掲載料金の試算もできます!!
≫ホワイトペーパー【「求職者に選ばれるための」採用ブランディング入門】無料ダウンロードはこちら
まとめ
本記事では、電気工事士、特に現場で作業を行う方を採用する際に、「人材紹介(有料職業紹介)」を利用することが、なぜ法的リスクを伴うのかを解説しました。
あわせて、人材紹介以外の採用手段についてもご紹介しました。
- 現場作業を行う電気工事士の人材紹介は、職業安定法により原則禁止されている
- 施工管理技士は管理業務中心のため人材紹介が可能な場合があるが、電気工事士は直接作業に従事するため法的扱いが異なる
- 法律を守った採用方法としては、自社サイトやSNSでの応募や、求人サイトを通した応募などが有効的
- 特に電気工事士のような専門性が高い職種は、業界専門の求人サイトを活用することで、資格保有者・経験者に効率よくアプローチできる
- 専門求人サイトは業界に精通したサポート体制があるため、急募案件への対応や採用コストの削減にもつながるメリットがある
企業が法令を守りながら採用活動を行うことは、持続的な経営の土台となります。
今回ご紹介した情報が、現在の採用戦略を見直すきっかけとなり、より安全で確実な手法を選ぶ参考になれば幸いです。
たとえば、自社の採用サイトやSNSを活用して直接応募を促したり、電気工事士に特化した求人サイトを利用したりといった方法も有効です。
こうした適切なアプローチを選ぶことで、本当に求める人材と安全に出会い、事業のさらなる成長につながることを願っております。
\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
掲載料金の試算もできます!!
≫ホワイトペーパー【「求職者に選ばれるための」採用ブランディング入門】無料ダウンロードはこちら
ご案内|「工事士.com」なら、採用成功まで伴走します
工事士.comは、電気・設備業界に特化した求人サイトです。
全国の若手や有資格者が多数登録しており、中小企業の採用成功事例も豊富にあります。
求人票の作成はもちろん、“見せ方”や“伝え方”の工夫までしっかりサポート。
貴社の魅力を引き出し、応募につながるよう伴走します。
- 採用課題のご相談だけでもOK
- 掲載相談・資料請求は無料
\電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
採用課題のご相談だけでもOKです!!



