建設業界の人手不足の実態と原因は?解決策のポイントは採用力強化!
建設業界においては、高齢化が進む一方で若手人材の参入が少なく、深刻な人材不足が続いています。
特に、「2025年問題」が建設業に与える影響は大きく、大量のベテラン労働者が定年を迎えようとしています。人手不足が続けば工期の遅延や受注機会の損失に繋がり、企業経営に大きな影響を及ぼすでしょう。
この記事では、建設業界が人手不足に陥っている原因を分かりやすく解説するとともに、企業が今から取り組むべき現実的な解決策をご紹介します。
- 建設業の人手不足の実態の最新情報
- 人手不足が深刻化する3つの構造的原因
- 建設業の人手不足の根本的解決策となる「採用力強化」
- 業務効率化で建設業の人手不足をカバーする方法
- 建設業の人手不足についてよくある質問
人手不足や採用活動にお悩みの経営者や採用担当者の皆さまは、ぜひご覧ください。

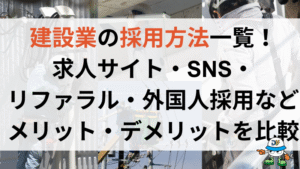
【2025年最新】建設業界の人手不足の実態
建設業界の人手不足は一時的なものではなく、統計にもはっきりと表れています。
国土交通省が公表している「建設労働需給調査」では、2025年の7月時点における技能労働者の過不足率は、全国平均で約1.6%の不足となっており、人員不足が続いています。また、人手不足の深刻さは就業者数の推移からも分かります。
こうした現状を踏まえると、人手不足は今後さらに深刻化すると予測され、企業にとって早急な対策が不可欠です。
ここでは、建設業界の人手不足の実態を知るために、技能労働者の過不足率や就業者数について詳しくみていきましょう。
- 過不足率と職種別詳細データ
- 建設就業者数の長期推移と業界縮小の実態
過不足率と職種別詳細データ
建設業界の各職種の過不足率を見ると、不足している職種が多くあります。
労働市場における「過不足率」とは、需要に対し供給(人材)がどれだけ足りていないかを示す指標です。
計算方法は以下のとおりです。
過不足率=不足人員数÷必要人員数×100
国土交通省の「建設労働需給調査」によると、2025年7月時点において、建設業界8職種の過不足率は全国平均で1.6%の不足でした。前月1.1%の不足と比べて不足幅が拡大しており、慢性的な人手不足が解消されていません。
また、職種別の過不足率を見てみると、建設業界の主な8職種のうち、6職種が「不足」となっています。
■ 建設業 職種別(8職種)の過不足率
| 職種 | 過不足率(2025年7月度) |
|---|---|
| 型わく工(土木) | 2.7% |
| 型わく工(建築) | △1.4% |
| 左官 | 1.7% |
| とび工 | 3.7% |
| 鉄筋工(土木) | 1.7% |
| 鉄筋工(建築) | △0.8% |
| 電工 | 1.2% |
| 配管工 | 1.2% |
| 計 | 1.6% |
特に、型わく工(土木)やとび工などは不足率が高く、需要に応じた人員を確保できない状況になっています。

建設就業者数の推移と業界縮小の実態
建設業界全体の就業者数は、長期的に減少しています。
ピーク時の1997年と2024年で比較すると下表のとおりになります。
■ 建設業界の就業者数の推移
| 西暦 | 建設就業者数 |
|---|---|
| 2024年 | 477万人 |
| 1997年 | 685万人 |
| ピーク時との差 | ー208万人 |
建設業界の就業者数は、27年間で200万人以上が減少したことになり、業界全体の労働力基盤が急速に弱体化している証拠と言えます。
また、地域別に見ると、都市部では大型再開発やインフラ更新工事が相次ぐ一方、地方では特に東北や北陸の人手不足が目立っています。
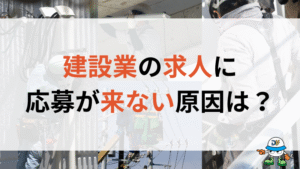
\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
掲載料金の試算もできます!!
人手不足が深刻化する3つの構造的原因
建設業界の人手不足は一時的な景気変動ではなく、業界全体に根差した「構造的な原因」が背景にあります。
- 労働人口の高齢化と若手離れの実態
- 建設業が敬遠される給与・労働条件の実態
- 2025年問題と建設需要拡大の矛盾
人手不足が深刻化している原因について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
労働人口の高齢化と若手離れの実態
建設業界の労働者は、高齢化が著しく、若手離れが深刻な課題です。
一般社団法人 日本建設業連合会の調査によると、過去20年において、29歳以下の若年層が約88万人から約56万人に減少し、65歳以上は37万人代から80万人台まで大きく増加しています。
また、厚生労働省の調査によると、55歳以上の比率は全体の約34%なのに対して、29歳以下は約11%にとどまり、年齢構成は「逆ピラミッド型」に近づいています。
このように、熟練職人の引退が進む一方で、若手の参入が少ないため、現場で必要な高度技能が十分に伝承されず、技術の空洞化が懸念されています。人材の高齢化と若手不足によって、建設業界は今まさに技能継承の危機に直面していると言えるでしょう。

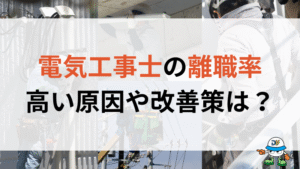
建設業が敬遠される給与・労働条件の実態
建設業の人材不足を語る上で避けられないのが、労働環境の厳しさです。
建設業界は依然として長時間労働などが根強く、企業によっては、特に繁忙期には休日返上で現場が続く可能性も考えられるでしょう。
この背景には工期の短さや天候リスクがあり、柔軟な働き方を取り入れにくい構造的な課題があります。また、建設業界に対しては「3K(きつい・汚い・危険)」というイメージもいまだに強く、若年層や女性にとって敬遠される要因となっています。
こうした問題に対して、国土交通省は「建設業における働き方改革」を推進しており、週休2日制の導入や適正工期の確保、給与水準の改善を目指しています。しかし、現場ではまだ改革が十分に浸透しておらず、就業希望者の確保には時間を要するのが現状です。
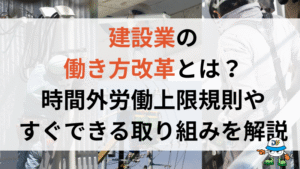

2025年問題と建設需要拡大の矛盾
建設業界に迫っている「2025年問題」とは、団塊世代の大量退職により、長年現場を支えてきたベテラン技能労働者が一気に減少することを指します。
建設就業者の約34%が55歳以上であるため、熟練職人の多くが現場を離れる可能性が高く、技能承継の空洞化と人員不足が一気に加速すると予想されています。
さらに「働き方改革関連法」によって、時間外労働の上限規制が始まったことで、従来の長時間労働による人手不足のカバーが困難になっています。
一方で、建設需要は拡大傾向にあります。国土交通省が定める「社会資本整備重点計画」では、道路や鉄道・空港などの公共インフラ整備の生産性向上が求められるなど、インフラの老朽化対策や大都市圏での再開発、災害復旧・防災投資が相次いでいます。
以上のように、2025年以降の建設業界は「需要拡大」と「供給不足」が同時進行する時代に突入するため、従来のやり方では事業継続が難しくなるでしょう。
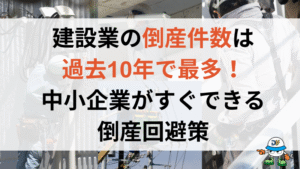
\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
掲載料金の試算もできます!!
建設業界の人手不足の根本的解決策となる「採用力強化」
建設業界の人手不足を解消するためには、単に求人を出すだけでなく「選ばれる企業」になることが不可欠です。
人材確保は経営の最重要課題であり、今後は人材確保に向けて、求人サイトを活用した人材確保や給与体系の透明化、福利厚生の拡充などを行う必要があります。
ここでは、採用力を高めるための解決策について解説していきます。
- 応募者が集まる求人の作り方と改善ポイント
- 応募者に選ばれる労働環境改善のポイント
採用力を強化する取り組みは、長期的な人材確保だけでなく企業ブランドの向上にも繋がるため、今こそ本格的に着手すべき課題と言えるでしょう。
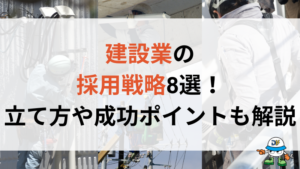
応募者が集まる求人の作り方と改善ポイント
人材不足の建設業界においては、いかに求職者に選ばれる求人を作るかが、応募数増の大きなポイントになります。
電気・設備業界特化型求人サイトの「工事士.com」でこれまで掲載されてきた求人の傾向として、具体的には、特に求職者からの関心が高い下記項目について詳細情報を記載するのが効果的です。
■ 応募者が集まる求人を作るために重視するべき項目
- 資格取得の支援制度
- 福利厚生
- 休日
- 各種手当
例えば、企業の特徴を紹介する際にも、「働きやすい職場です」のような曖昧な表現だけでは響きません。
休日や平均残業時間については、具体的な数字を提示することで、求職者が安心して応募しやすくなるでしょう。
次に、福利厚生や研修制度を魅力的に打ち出す工夫も欠かせません。資格取得支援や安全研修、住宅手当や家族手当といった制度を、単なる羅列ではなく「キャリア形成を支える仕組み」として表現すると訴求力が高まります。
また、若手人材には成長や安定、社会貢献といった価値観が響きやすいため、求人文面でも「未経験から国家資格を目指せる」や「残業が少ない」といったポジティブな表現を心掛けましょう。
従来の3Kイメージを払拭し、「安心」「安定」「将来性」を前面に出すことが、応募者を集める求人作成の最大のポイントです。
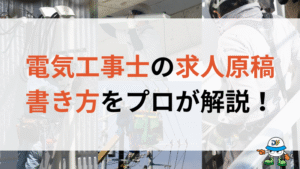
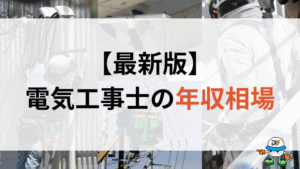
応募者に選ばれる労働環境改善のポイント
採用活動を成功させるためには、求人条件だけでなく職場環境の改善が欠かせません。
まず、週休2日制の導入は応募者が最も重視する要素の一つです。初めから週休2日制が難しい場合は、段階的な導入から始めてみるのも良いでしょう。
また、工期設定を工夫し、残業時間を少しずつでも短縮していくことで、長時間労働の是正に繋がります。
職場環境の改善も大きなポイントで、日常的に働きやすさを感じられる工夫は離職防止に直結します。また、キャリアパスや昇進制度を明確にすることで、若手層は「将来像」をイメージできるようになるため、安心して長期的に働ける職場になります。
現場の改善を一歩ずつ進めていくことが、応募者に選ばれる企業への第一歩となるでしょう。

\工事士.com掲載後の効果や事例をご紹介 /
掲載企業様のインタビュー掲載中!!
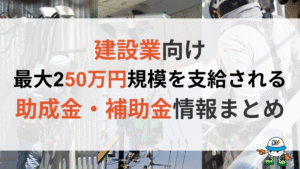
業務効率化で建設業界の人手不足をカバーする方法
建設業の人手不足解決には、採用力強化だけでなく、業務効率化による生産性向上が欠かせません。
ICTやDXツールの活用により、測量や施工管理の作業時間を削減することが期待できます。
- ICT・DXツール導入の段階的アプローチ
- 中小企業でも実現可能な省人化手法
ICT・DXツール導入の段階的アプローチ
人手不足を補うために注目されているのが、ICTやDXツールの段階的導入です。
まず基盤となるのはBIM(Building Information Modeling)です。設計段階から3Dモデルを活用することで、数量計算や干渉チェックの自動化、施工計画の精度の向上による設計・施工の効率化やミス削減などが期待できます。
次に、ドローンを使った測量や進捗管理も効果的です。従来数日かかっていた現場測量を数時間で終えられ、進捗写真の定期的な取得によって現場の可視化も容易になります。
さらには、AIやIoTを活用した機械制御やセンサー管理による作業の自動化・省人化も進んでいます。
こうしたツールの段階的導入を積み重ねると、中小企業でも現実的に生産性を高めることにつながります。
中小企業でも実現可能な省人化手法
大規模な投資が難しい中小建設業においても、省人化や効率化を進める方法は数多くあります。
まず取り入れやすいのが、低コストで導入できるクラウド型の施工管理ツールです。
インターネット環境さえあれば利用でき、図面や工程表、写真をオンラインで共有できるため、現場と事務所間のやり取りを大幅に効率化に繋がります。
また、スマートフォンやタブレットの活用も効果的です。従来は紙で行っていたチェックリストや作業報告をアプリで入力すれば、事務作業の時間削減につながり、リアルタイムでの進捗管理も可能になります。
こうした取り組みは、結果的にプロジェクト全体の管理が円滑になり、少ない人数でも現場を回せる仕組み作りができます。特に中小企業では、現場に負担をかけず効率化を進めることが、人手不足の解決策となるでしょう。
\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
掲載料金の試算もできます!!
電気設備の求人掲載なら「工事士.com」にご相談ください!
建設業界の中でも、特に電気設備関連の採用でお悩みの方には「工事士.com」がおすすめです。
工事士.comは電気設備業界に特化した求人サイトのため、電気関連の資格保有者や未経験ながらも業界への転職意欲が高い求職者が集まっています。
そのため、他媒体と比べて、よりマッチング率の高い採用活動が期待できます。
■ 電気設備業界特化の求人サイト「工事士.com」の特徴
- 月間サイト利用者45万人、うち63%が30代以下で若手層へのアプローチも可能
- ユーザーの電気工事士資格保有者率68%、未保有者においても業界への関心が高いため、求める人材像とマッチングしやすい
- 求人票は専属ライターが作成、掲載後も何度も修正可能で運用管理が楽
- 掲載料金は大手企業の1/3程度。同じ料金なら掲載期間は約3倍
求人の掲載は最短翌日から可能です。
「現在の採用活動では応募が来ない」とお困りの方は、ぜひ一度「工事士.com」にご相談ください。
\電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
掲載料金の試算もできます!!
建設業界の人手不足に関するよくある質問(FAQ)
建設業の人手不足について、経営者や人事担当者の方からよく寄せられる質問にお答えします。
人材確保や採用戦略を検討する際の参考にしてください。
- 建設業の人手不足はなぜ起きているのですか?
- 「建設業の人手不足は嘘」「自業自得で当たり前」と言われるのはなぜですか?
- 建設業の人手不足の今後はどうなりますか?解消の見込みはありますか?
- 人手不足倒産を防ぐための対策にはどのようなものがありますか?
建設業の人手不足はなぜ起きているのですか?
建設業の人手不足は、複数の構造的な問題が重なって発生しています。
まず挙げられるのが、就業者の高齢化と若者離れです。厚生労働省の調査によると、建設業界の就業者の年齢構成は、55歳以上の比率が全体の約34%なのに対し29歳以下は約11%にとどまっています。
次に、「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージが根強く残っていることです。屋外作業による天候の影響、高所での危険な作業、長時間労働といった厳しい労働環境のイメージが、若年層の建設業離れを加速させています。
さらに、賃金・労働条件の問題も深刻です。国土交通省の調査によると、建設業の年間実労働時間は全産業平均より346時間も長く、年間出勤日数も全産業平均より30日多いというデータがあります。また、建設業の平均賃金は製造業と比較して伸び悩み、40代後半で頭打ちになる傾向があります。
こうした複合的な要因が絡み合い、建設業界は他業種と比較しても深刻な人手不足に陥っているのです。
「建設業の人手不足は嘘」「自業自得で当たり前」と言われるのはなぜですか?
このような厳しい意見が出る背景には、いくつかの理由があります。
まず、過去の公共事業縮小期のイメージが残っていることが挙げられます。バブル崩壊後から2010年代初頭にかけて建設投資は大幅に縮小し、「仕事がない」時代が続きました。リーマンショック後には「日給1万円も稼げない」「ワンコイン大工」と呼ばれる職人が現れた時期もあり、このイメージから「人手不足は嘘だ」と思われることがあります。
また、労働環境の改善が長年後回しにされてきたという指摘もあります。週休1日が当たり前という時代が長く続き、長時間労働や休日の少なさ、危険な作業環境など、他業界では改善が進んだ部分で建設業は遅れを取りました。「自業自得」という声は、こうした業界体質への批判から来ています。
しかし現在は、業界全体で働き方改革が進んでいます。2024年4月からは時間外労働の上限規制が建設業にも適用され、週休2日制の導入や給与改善、ICT活用による業務効率化など、労働環境の改善に取り組む企業が増えています。
こうした変化を知らないまま、過去のイメージで語られることが「嘘」「自業自得」という声につながっている面もあるのです。
建設業の人手不足の今後はどうなりますか?解消の見込みはありますか?
建設業の人手不足は今後さらに深刻化すると予測されています。
ただし、変化に対応できる企業とそうでない企業の二極化が進むでしょう。
ヒューマンリソシアの独自調査によると、2030年には建設技術者が約3.2万人、建設技能工は約23.2万人が不足すると試算されています。
また、2025年問題・2030年問題も深刻です。2030年には日本国内の人口の約3割が高齢者となるため、高齢化が進む建設業においても大量退職の波が押し寄せます。
一方で、完全な悲観論ではありません。建設業界では人手不足解消のために以下の変化が起きています。
■ 建設業界の人手不足解消に向けた変化
- 労働環境の改善:「働き方改革」の加速や賃金改善など
- DX・ICT化の進展:ドローンによる測量やICT建機の導入など
- 外国人材の活用:特定技能制度を活用した外国人労働者の受け入れ拡大
今後の見通しとしては、若手育成に投資し、デジタル化や業務効率化を進めた企業には人が集まり、そうでない企業はますます人手不足に苦しむという二極化が進むと予測されています。変化に対応できる企業にとっては、売り手市場を活かしたチャンスともいえる状況です。
人手不足倒産を防ぐための対策にはどのようなものがありますか?
人手不足倒産を防ぐためには、以下の対策が有効です。
■ 建設業の人手不足倒産を防ぐための対策
- 賃上げ・処遇改善
賃金の引き上げ、日給制から月給制への変更、各種手当の導入、「建設キャリアアップシステム(CCUS)」を活用した技能や経験に応じた適正な評価と処遇体制の構築など - DX化・業務効率化
施工管理アプリの導入による情報共有の効率化、ドローンやICT建機を活用した省人化、BIM/CIMによる設計・施工の効率化、クラウドサービスを活用した図面・資料の共有など - 採用ターゲットの拡大
従来の「工業高校電気科卒業生」といった限定的な採用ターゲットから、大卒者、異業種からの転職者、女性、外国人材への拡大、SNSやYouTubeを活用した情報発信で若年層へのアプローチ強化など - 労働環境の改善:週休2日制の導入、残業時間の削減、安全対策の強化、女性専用のトイレや更衣室の設置、清潔な休憩室の整備など
- 外注・アウトソーシングの活用:施工管理の事務業務の外部委託など
人手不足倒産は、単に人材が足りないだけではなく、賃上げ圧力・規制強化・資材高騰・融資返済といった複数の要因が重なった結果として起こります。企業が早めに対応を進めることで、倒産リスクを軽減し、持続的な経営基盤を築くことができるでしょう。
\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
掲載料金の試算もできます!!
まとめ
今回は建設業界の人材不足が深刻化している原因や採用強化による解決策、人手不足をカバーする方法について解説しました。
- 現在の建設業界は、1997年のピーク時に比べて就業者数が減少傾向にあり、慢性的な人手不足が続いている
- 建設業界の年齢構成は、55歳以上の割合が全体の約34%なのに対し、29歳以下の割合は約11%と高齢化が著しく、今後さらなる人材不足が懸念されている
- 建設業界の人手不足を解決するためには、採用力の強化が必要で、特に「応募が集まる求人作り」や「労働環境の改善」、さらには「業界特化型求人サイトの活用」が重要
建設業の人材不足を解消させるには、効果的な求人作成や労働環境改善で応募者を惹きつけるとともに、ICTやDXを活用して限られた人材で効率的に工事を進める工夫が欠かせません。
人材確保のために、まずは自社の現状を把握し、優先順位をつけて、段階的に施策を実行することが大切になります。その1つとして、建設業界専門の求人サイトの活用も効果的です。採用力を高めたい企業の皆さまは、建設業界専門の採用支援サービス 工事士.com への掲載をご検討ください。


