電気工事士の人材派遣は禁止!その理由と違反にならない採用方法を紹介
- 電気工事士を派遣し、施工といった対象除外業務に従事させることは、「労働者派遣法第4条第1項」によって禁止されている
- 電気工事業を含む建設業において派遣が禁止されている理由は、雇用が不安定で、安全管理や品質の担保が難しいため
- 違反した場合は、刑事罰や行政処分として営業停止や許可取消などの重いペナルティが科せられる場合がある
- 電気工事士の採用は、専門求人サイトやハローワーク、リファラル採用など、法令を遵守した方法を数多く活用できる
電気工事士を建設現場へ派遣し、電気工事業務を行わせることは、労働者派遣法によって禁止されています。
慢性的な人手不足に悩む電気工事会社にとって、派遣等によって即戦力人材を柔軟に確保したいというニーズは切実です。
しかし、厚生労働省や日本人材派遣協会も「電気工事は建設業務に該当し、派遣の対象外である」という見解を示しており、電気工事士を派遣として受け入れることはできません。
この記事では、こうした法的背景を正確に解説しつつ、違法行為を避けながら電気工事士を効率的に採用する4つの方法をご紹介します。
現場の人手不足により、電気工事士の派遣を検討されている方、電気工事士の採用でお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。
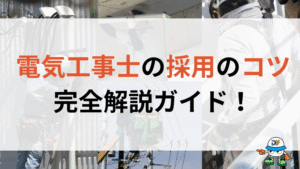
【結論】電気工事士の派遣は労働者派遣法により禁止されている

電気工事士を建設現場へ派遣し、現場作業に従事させることは禁止されています。
なぜなら、労働者派遣法において、派遣が禁止されている「建設業務」に電気工事が該当するためです。
まずは、この法的なルールについて詳しく見ていきましょう。
労働者派遣法第4条第1項による「建設業務」への派遣禁止
「労働者派遣法第4条第1項」では、一部の業務について労働者派遣事業を行うことを禁止しており、「建設業務」はその一つとして明確に定められています。
第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
条文にある通り、「建設業務」には建物の新築や改修だけでなく、修理や変更、解体、それらの準備作業まで幅広く含まれます。電気工事士が担う配線や配管工事なども、この建設業務に該当します。
そのため、電気工事士を派遣社員として建設現場の施工業務に従事させることは、法律で禁止されています。
電気工事が「建設業務」に該当する法的根拠
では、具体的にどのような作業が「建設業務」と見なされるのでしょうか。
一般社団法人日本人材派遣協会は、建設業務の具体例を13の事例に分類して示しており、その中の「事例8」に電気工事が明確に含まれています。
■ 建設業務の適用除外業務
事例1:ビル・家屋等の建築現場にて、資材の運搬・組み立て等を行う。
事例2:道路・河川・橋・鉄道・港湾・空港等の開設・修築などの工事現場で掘削・埋め立て・資材の運搬・組み立て等を行う(事例1・2共に施行計画の作成や、工程管理・品質管理などは含まない)。
事例3:建築・土木工事において、コンクリートを合成したり、建材を加工したりする。建築・土木工事現場での準備作業全般を含む。
事例4:建築・土木工事現場内で資材・機材を配送する(現場外からの資材の搬入は含まない)。
事例5:壁や天井・床の塗装や補修をする。
事例6:建具類等を壁や天井・床に固定する、あるいは撤去する。
事例7:外壁に電飾版や看板などを設置する、あるいは撤去する。
事例8:建築・土木工事現場内において、配電・配管工事をしたり機器の設置をしたりする。
事例9:建築・土木工事現場の入口の開閉や車両の出入りの管理・誘導をする。
事例10:建築・土木工事後の現場の整理・清掃(内装仕上げ)をする。
事例11:イベントなどを行う大型仮設テントや大型仮設舞台の設置をする(簡易テントの設営、パーティションの設置などは含まない。また、椅子の搬入や舞台装置・大道具・小道具の設置等も含まない)。
事例12:仮設住宅(プレハブ住宅等)の組み立てを行う。
事例13:建造物や家屋を解体する。
このように、電気工事士が現場で行う施工業務は、法的に建設業務と解釈されます。そのため、電気工事士の労働者派遣は実質的に禁止となっています。
派遣が可能な業務と禁止される業務の境界線
重要なのは、禁止されているのはあくまで現場での「施工業務」であり、「電気工事士」という資格を持つ人自体の派遣が禁止されているわけではない、という点です。
例えば、以下のような業務は建設業務に該当しないため、電気工事士の資格を持つ人が派遣社員として従事することも可能です。
■ 派遣の電気工事士が従事できる業務
- CADオペレーター
- 積算、見積もりなどの事務作業
- 施工管理(現場の工程管理、品質管理、安全管理など)
反対に、上記の目的で派遣された電気工事士に現場での施工業務を行わせた場合、法律違反となるため注意が必要です。
\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
掲載料金の試算もできます!!
電気工事士の派遣が禁止される理由
電気工事の現場は、高所作業や感電など常に危険と隣り合わせです。労働者派遣では、指揮命令者(派遣先)と雇用主(派遣元)が異なるため、安全や品質の責任が曖昧になるおそれがあります。
この「責任の分断」が重大な事故を引き起こしかねないため、法律で禁止されています。
それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
不安定な雇用形態を避けるため
建設業への派遣が禁止されている理由の一つに、労働者の雇用を守るという目的があります。
建設業の仕事は、案件ごとに場所、内容、期間がすべて異なる「受注生産」が基本です。さらに、一つの現場で多くの専門業者が協力して工事を進めるため、工事の進捗状況によって必要な人員が常に変動します。
もし、このような現場に派遣労働が認められるとどうなるでしょうか。「担当工程が早く終わった」「前工程の遅れで作業に入れない」「急な設計変更で工事が止まった」といった現場の都合で、労働者は本人の意思と関係なく契約を打ち切られ、不安定な働き方を強いられるリスクがあるのです。
このような事態を防ぎ、労働者を保護する観点から、建設業務への派遣は法律で禁止されています。
現場の安全と品質を確保するため
建設現場、特に電気工事では、感電や火災といった重大な事故を防ぐための「安全管理」と、建物の機能を長期間保証するための「施工品質の担保」が何よりも重要です。
しかし、労働者派遣の仕組みでは、これら両方の確保が難しくなるという問題があります。
■ 正社員と派遣労働者における安全管理体制の違い
| 項目 | 正社員 | 派遣労働者 |
|---|---|---|
| 雇用 | 自社 | 派遣元企業 |
| 指揮命令 | 自社 | 派遣先企業 |
| 安全管理 | 雇用と指揮命令が一体で、 責任の所在が明確 | 責任の所在が曖昧になりやすい |
| 品質管理 | 自社基準で教育・管理し、 品質を統一しやすい | 現場ごとの基準に依存し、 品質が不安定になりやすい |
このように、正社員は「雇用」と「指揮命令」が一体であるため、安全と品質に対する責任の所在が明確です。
一方で派遣労働者の場合、この二つが分離することで、「安全と品質を、最終的にどこが担保するのか」という点が曖昧になります。
この構造的な問題が、重大な事故や品質低下を招くリスクとなるため、建設業への派遣は法律で禁止されているのです。
\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
掲載料金の試算もできます!!
派遣禁止に違反した場合のリスクと罰則

電気工事士を派遣し、派遣対象除外業務に従事させた場合、事業者は労働者派遣法違反として厳しい罰則の対象となる可能性があります。
違反が認められた場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されたり、行政処分として事業停止や許可取消といった重いペナルティが発生したりする恐れがあります。
過去には派遣契約と知りながら電気工事を実施させた企業が摘発された例もあるため、「知らなかった」では済まされません。今一度しっかり確認しておきましょう。
刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
労働者派遣法に違反して、電気工事士を派遣し、派遣対象除外業務に就業させた場合、刑事罰が科される可能性があります。
具体的には、労働者派遣法第59条第1号により、以下の罰則が科されます。
適用除外業務について労働者派遣事業を行った者は、法第59条第1号に該当し1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
これは法人ではなく、経営者や担当責任者個人にも適用される可能性がある点に注意が必要です。さらに、違反の内容や頻度、悪質性によっては、労働局による調査や刑事告発に発展する場合もあり、企業の社会的信用に大きなダメージを与える恐れがあります。
また、「派遣元が手続きをしているから問題ないだろう」といった認識は非常に危険です。派遣先企業であっても、違法行為に加担したとみなされれば、等しく責任を問われます。電気工事士の採用は、必ず合法的な手段を選ぶことが、企業を守る最大の防御策となります。
行政処分(事業停止命令・許可取消等)
電気工事士を派遣で適用除外業務に就業させた場合、企業は刑事罰にとどまらず、労働局からの行政処分を受ける場合もあります。
それぞれの行政処分については、下記のとおりです。
| 処分 | 詳細 |
|---|---|
| 指示 | ・最も軽い処分で、違反に対する是正を求める措置 ・外部に公表されることは少ないものの、再発時には処分が重くなるリスクをはらんでいる |
| 事業停止命令 | ・一定期間、一部建設業務の実施を禁止される処分 ・受注停止により企業の売上や信用に直接ダメージを与える恐れがある |
| 許可の取消し | ・建設業の許可そのものが取り消される ・事実上の営業停止となるため、企業活動の継続が困難になる |
特に建設業界では、元請企業や取引先との信頼関係が事業の基盤となるため、一度でも行政処分を受けると、長期的な取引停止や入札資格の喪失に繋がりかねません。
法令を軽視した判断は、企業経営そのものを揺るがす重大なリスクになりやすいため、採用担当者・経営層ともに十分な認識が必要です。
実際の違反事例と企業への影響
建設会社で実際に起こった派遣に関する違反事例をご紹介します。
■ 労働者派遣法違反の事件例
令和3年、とある建設会社が、労働者派遣法違反の疑いで刑事告発されました。同社は厚生労働大臣の許可を受けることなく、建設業務(禁止業務)への労働者派遣を実施していました。
具体的には、住宅補修工事現場において、同社が雇用する作業員を別の建設会社に派遣し、建設作業に従事させていました。派遣された作業員は現場で電線に接触し感電死する重大な労働災害が発生しており、この事故をきっかけに違法派遣が発覚しました。
この事例は、建設業務への労働者派遣が原則禁止されている理由を如実に示しています。
適切な安全管理体制が確保されない違法派遣は、労働者の生命に関わる深刻な結果を招く可能性があります。電気工事士においても、同様のリスクが存在するため、派遣での業務従事は厳格に禁止されているのです。
\工事士.com掲載後の効果や事例をご紹介 /
掲載企業様のインタビュー掲載中!!
電気工事士を適法で採用する4つの方法

電気工事士を適法かつ実用的に採用する手段は複数存在します。
したがって、人手不足を抱える企業でも、法令を遵守しながら人材を確保することは十分可能です。
ここでは、電気工事士を適法に採用する4つの方法を紹介します。
特に効果的なのが、電気工事士専門の求人サイトを活用する方法です。求職者の多くが業種特化の求人を探しているため、即戦力とのマッチングが期待できます。
いずれの方法も、労働者と企業が直接雇用契約を結ぶ形となるため、違法性のリスクがなく、安定的な人材確保に繋がります。
電気工事士専門求人サイトでの採用
電気工事士を適法かつ効率的に採用したい場合に最も効果的なのが、業界特化型の求人サイトの活用です。
業界特化型の求人サイトには、現場経験者や有資格者などの求職者が集まっているため、一般の求人サイトと比べてマッチング精度が高く、採用までのスピードも早いのが特徴です。
さらに、業界に特化していることで、求人原稿の内容やアピールポイントも電気工事士目線で最適化されており、ミスマッチが少なく定着率の高い採用を目指せます。
一般的な総合求人サイトでは応募者の職種経験が浅い、あるいは資格を持っていないケースも多く、選考や教育に余計なコストがかかる傾向があります。
その点、専門求人サイトでは実務経験や資格保有を条件に絞った募集が可能なため、より確実に即戦力人材を確保できます。違法な派遣に頼らず、確実に電気工事士を採用したい企業にとって、専門求人サイトは非常に有効な選択肢と言えるでしょう。
業界特化型求人サイトの中でも、電気設備業界の求人に特化した「工事士.com」は、これまでに10,000社以上の電気工事会社の求人を掲載してきており、満足度97%を獲得しております。(※当社調べ)
求人を掲載するまでの手間と時間も最小限にでき、最短翌日からの掲載も可能です。
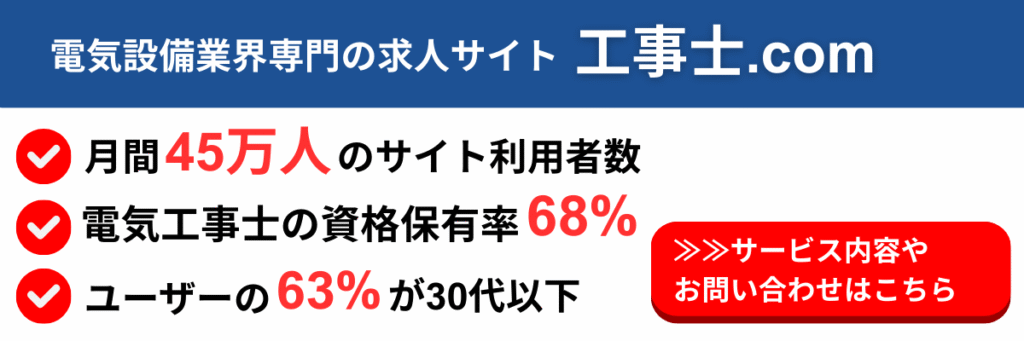
効率よく人手不足を解消したいとお考えの方は、一度「工事士.com」にお気軽にお問い合わせください。

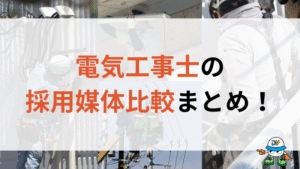
ハローワークでの直接求人募集
電気工事士の採用手段としては、ハローワークを活用する方法もあります。
ハローワークは厚生労働省が運営する公的な職業紹介機関であるため、無料で求人を掲載できる点が大きなメリットです。
特に、地域密着型の採用を希望する中小企業にとっては、地元の求職者にリーチしやすい手段として根強い人気があります。
一方、ハローワークでの求人募集にはデメリットもあります。
■ ハローワーク採用のデメリット
- 特に若手層のハローワーク利用率が低下している
- 求める人材のミスマッチが発生しやすい
- 募集開始から採用までに時間がかかる
- 求人票の形式が決まっているため自由度に欠ける
ハローワークはスピード感や訴求の面で課題があるため、同じエリアで多数の求人が掲載されていると、競合他社に埋もれやすい点にも注意が必要です。
そのため、ハローワークは、コストを抑えつつ中長期的にじっくり人材を探したい企業に向いている手法と言えるでしょう。短期での採用が必要な場合は、専門求人サイトなどと併用するのが効果的です。
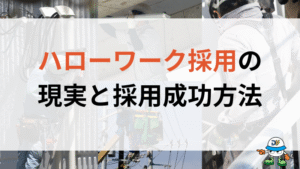
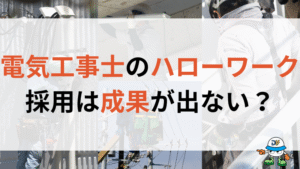
リファラル採用(従業員紹介制度)
リファラル採用とは、既存の従業員に知人・友人を紹介してもらい採用につなげる制度です。
電気工事士のように専門資格や現場経験が求められる職種では、同業種のネットワークが活かされやすく、実務に即した人材と出会える可能性があります。
紹介された人材は、すでに現場を知る従業員から仕事内容や社風を聞いた上で応募してくるため、入社後のミスマッチが少なく、定着率が高くなりやすい点も特徴です。制度として定着させるには、紹介者にインセンティブ(報酬)を支給するなど、社内制度として仕組み化することが効果的です。
ただし、紹介に頼る以上、従業員の人脈に依存することとなり、常に安定した人材確保ができるとは限りません。特に少人数の会社や新設企業では、紹介できる候補者がそもそも少ないこともあります。
したがって、リファラル採用は、あくまで他の手法と組み合わせる「補助的手段」として活用するのが現実的です。費用を抑えつつ質の高い人材を狙いたいときに、選択肢の1つとして取り入れてみましょう。
リファラル採用について、より詳しく知りたい方は下記記事をあわせてご確認ください。
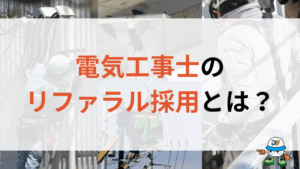
自社ホームページ・SNSでの採用活動
電気工事士の採用において、自社ホームページやSNSを活用する手法も有効な選択肢の一つです。
特に、企業の信頼性や雰囲気を求職者に伝えるうえで、自社メディアは自由度が高く、ブランディングにも繋がります。
例えば、採用専用ページを設けて、仕事内容や社員インタビュー・現場の写真・福利厚生などを詳しく掲載すれば、企業のリアルな魅力を伝えられるため、応募へのハードルを下げる効果が期待できます。
しかしその一方で、ホームページやSNSはすぐに効果が出るものではなく、一定の認知度を築くまでに時間がかかってしまいます。また、継続的な情報発信や更新作業には人的リソースも必要です。
そのため、ホームページやSNSは中長期的な採用戦略の一環として継続的に運用し、他の即効性の高い採用手法と並行して活用すると良いでしょう。会社の魅力を伝える「広報」としての役割も果たすため、長期的には人材確保の強力な武器になります。
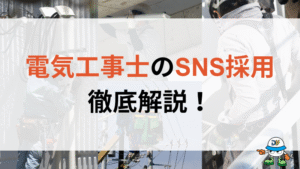
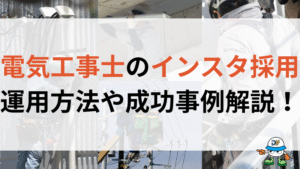
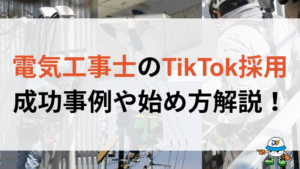
\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
掲載料金の試算もできます!!
電気工事士採用で避けるべき落とし穴
電気工事士を派遣し、派遣対象除外業務に従事させることは法律で禁止されていますが、「人材紹介なら大丈夫なのでは?」「一時的な応援なら派遣扱いにならないのでは?」といった誤解が多く見られます。
しかしながら、派遣と職業紹介を混同して契約を結んでしまうと、後に違法と判断される場合もあります。こうした誤解は、法令違反のリスクだけでなく、発注先や元請からの信頼喪失につながる恐れもあります。
安心して採用活動を行うためには、事前に正しい知識を持っておくことが大切です。また、困ったことがあれば、専門家や労働局に相談しながら進めましょう。
人材紹介も派遣も両方禁止?混同しやすいポイント
電気工事士の採用において特に誤解されやすいのが、派遣と人材紹介の違いです。
派遣は「雇用主は派遣会社、指揮命令は派遣先」という仕組みです。なお、「労働者派遣法第4条第1項」により、電気工事業を含む建設業務への派遣の従事は禁止されています。
一方で人材紹介は「雇用主は採用企業」です。そのため一見すると合法に思えますが、「職業安定法第三十二条の十一第一項」によると、建設業務においては有料職業紹介も禁止対象とされています。
したがって、電気工事士を建設現場で就業させる目的で派遣や人材紹介として利用することは、どちらも違法と見なされる可能性が高いです。「派遣ではなく、紹介なら問題ない」と誤解して契約を結んでしまうと、後に労働局から是正を受ける恐れもあります。
電気工事士の採用においては、派遣と紹介を混同せず、直接雇用の形で採用することが合法ルートであると理解しておきましょう。
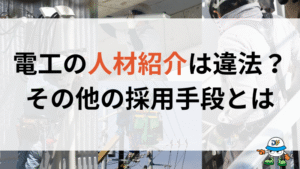
違法採用にならないための確認ポイント
電気工事士の採用を進める際、知らないうちに違法な派遣や紹介に該当してしまうケースは少なくありません。
特に建設業務においては、派遣も人材紹介も禁止されているため、採用担当者は常に注意が必要です。
例えば以下のようなチェックリストを作成するなどして、実務上の誤りを防ぎましょう。
■ 採用前に確認すべきチェックリスト
- 契約形態は「派遣契約」になっていないか
- 「人材紹介サービス」を通じて現場就業させようとしていないか
- 雇用主が自社であることを明確にしているか
- 雇用契約書に自社名が記載されているか
- 業務指揮命令を行うのが自社であるのを確認したか
- 法的に認められた採用ルート(求人サイト、ハローワーク等)を利用しているか
採用活動はスピードも重要ですが、法令遵守を最優先に進めることが、長期的に企業を守る最大の対策となります。
\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /
掲載料金の試算もできます!!
まとめ
この記事では、電気工事士の派遣が禁止されている理由や違反した場合のリスクと罰則、適法を用いた採用方法について解説しました。
- 電気工事士を派遣し、施工といった対象除外業務に従事させることは、「労働者派遣法第4条第1項」によって禁止されている
- 電気工事業を含む建設業において派遣が禁止されている理由は、雇用が不安定で、安全管理や品質の担保が難しいため
- 違反した場合は、刑事罰や行政処分として営業停止や許可取消などの重いペナルティが科せられる場合がある
- 電気工事士の採用は、専門求人サイトやハローワーク、リファラル採用など、法令を遵守した方法を数多く活用できる
電気工事士の採用で重要なのは、派遣や人材紹介に依存せず、正しい採用ルートを選ぶことが企業の信頼と経営の安定につながるという点です。法令を順守しつつ、長期的に人材を育成・確保できる体制を整えていきましょう。


